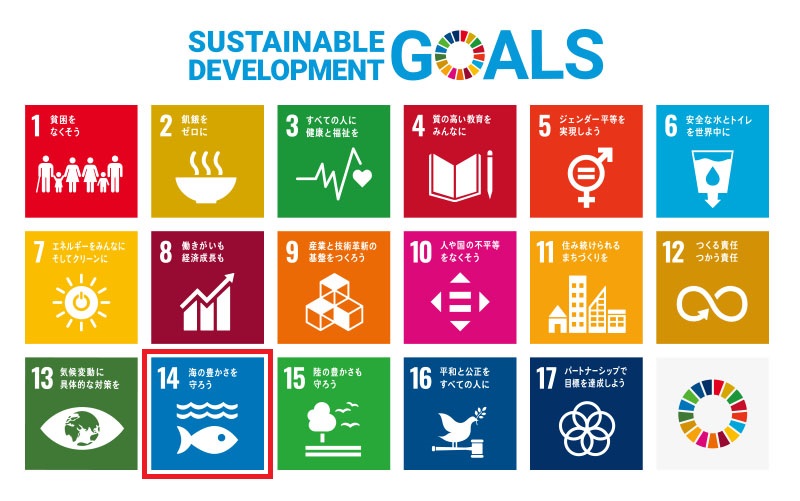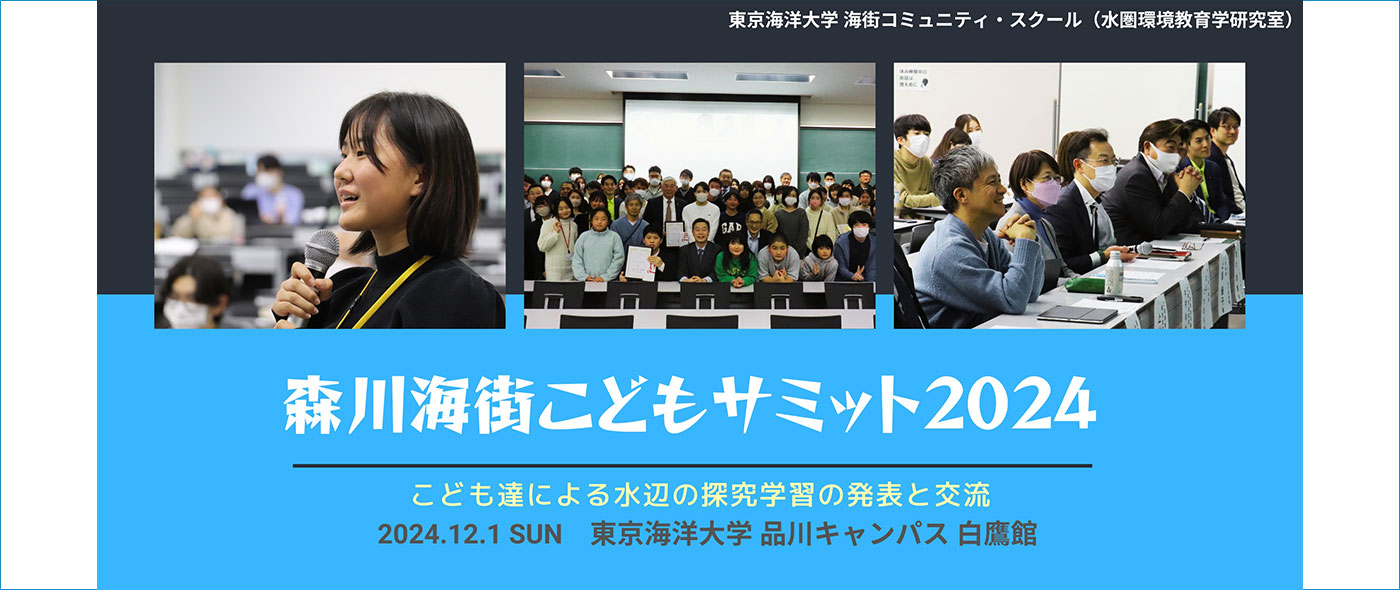マグロ・カツオ漁の未来を守る1億740万ドルの支援 - コンサベーション・インターナショナルと太平洋共同体が漁業コミュニティの気候変動対策のために歴史的な資金を確保
気候変動によるマグロ・カツオ資源の分布変化問題が太平洋諸島の経済に与えるリスクを軽減し、食料安全保障の解決策を提供
コンサベーション・インターナショナルと太平洋共同体(SPC)は、太平洋島しょ国の14カ国が、マグロ・カツオ漁によって得られている経済的・社会的利益が気候変動の影響によって損なわないよう支援するため、緑の気候基金(Green Climate Fund:GCF)から1億740万ドルの大規模な助成金を獲得しました。この歴史的な規模の助成は、同地域への気候対策資金としては過去最大級で、世界最大の海洋気候適応の取り組みとなります。「ザ・リージョナル・ツナ・プログラム」と名付けられた本プログラムはまた、追加的に4930万ドルの共同出資を集め、総額は1億5680万ドルに上ります。太平洋地域経済の基盤となるマグロ・カツオ漁業が海洋温暖化の影響に適応し、マグロ・カツオ漁業が地域社会の食料安全保障に大きく貢献するよう支援します。
クック諸島、フィジー、ミクロネシア連邦、キリバス、マーシャル諸島、ナウル、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ツバル、バヌアツの14カ国は、世界のマグロ・カツオ漁獲量の3分の1を管理する国であり、数十年にわたり資源を持続的に管理してきました。同時に、気候変動に対する責任が最も小さい国々でもあります。日本もこれらの地域、特にフィジーやバヌアツ、マーシャル諸島などからのマグロを頼っているため、同地域の安全保障は日本人の生活を支える上でも大切です。
マグロ・カツオ漁は、食料供給だけでなく、地域で数万人の雇用を支えており、経済的安全保障の面でも重要です。さらに9か国においては、マグロ漁業の参入に関連する税収が政府歳入の平均34%を賄っています。サンゴの白化など、環境変化による沿岸魚種の減少も重なり、太平洋コミュニティは、ますますマグロ漁への依存を強めています。
しかし、コンサベーション・インターナショナルとSPCの共同研究によると、海水温の上昇の影響でマグロ・カツオ資源が現在の各国の領海から公海に移動した場合、これらの国が現在マグロ・カツオ漁から得ている利益が大きく減ってしまうリスクが高いことが示されました。その研究では、気候変動の影響で2050年までにマグロ・カツオ資源の分布に変化が起こり、太平洋諸島の平均漁獲量は10-30%減少、年間の損失は合計4,000万ドルから1億4,000万ドルにのぼると予測されています。この損失は、マグロ漁に頼るそれぞれの国にとって、年間政府歳入の8~17%に相当する額になります。
本プログラムは、現在の経済的利益を太平洋島しょ国がこれからも維持することができるよう、これまで50年以上にわたる科学、研究、エビデンスに基づいた意思決定に基づき、気候変動適応策を支援するものです。
沿岸コミュニティの食料安全保障を強化するために、魚群集積装置(Fish Aggregation Devices :FAD)の使用を拡大し、混獲を改善したり、小規模漁業によるマグロ資源へのアクセスを増やします。FADの活用は、地元コミュニティの資源アクセスを高めるだけでなく、漁船で高速で移動するマグロを追い続ける必要がないので、燃料の削減にもなります。最終的に太平洋地域コミュニティのFAD活用を高め、食料安全保障を支える国家インフラの一部として定着させることを目指しています。
本プログラムは、SPCとフォーラム漁業庁(FFA)、オーストラリア連邦科学産業研究機構(CSIRO)などの地域パートナーとともに実施する予定です。
■コンサベーション・インターナショナル
すべての人々のウェルビーイング達成のために、自然保護を通じて持続可能な社会の実現を目指す国際環境NGO。現地コミュニティから政府まで、多様なパートナーシップを軸に、科学的知見に基づく戦略と革新的な手法を組み合わせ、世界70以上の国と地域で実践活動を続けている。
https://www.conservation.org/japan
■SPC *Pacific Community(SPC):
太平洋共同体の略称で、太平洋地域の持続可能な開発を支援するために設立された政府間組織。1947年に設立され、現在は27の国と地域が加盟している。SPCは、科学、技術、イノベーションを通じて地域の発展を促進し、特に海洋科学や漁業管理、公共保健、地質学、エネルギー、農業などの分野で重要な役割を果たしている。
https://www.spc.int/
■緑の気候基金(Green Climate Fund):
気候変動と戦う世界的な取り組みに野心的かつ大きく貢献するために設立された多国間基金。GCFは、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)とパリ協定の目標達成に貢献し、持続可能な開発という観点から、温室効果ガスの排出を制限または削減し、気候変動に適応するための途上国への支援を提供することで、低排出で気候変動に強い開発経路へのパラダイムシフトを促進することを目指している。
■マグロ・カツオ資源の分布変化問題とは
海水温の上昇により、マグロ・カツオの生息域が太平洋島嶼国の排他的経済水域(EEZ)外へ移り、これらの国々の漁獲量が減少すると予測されている。この問題は、温室効果ガス排出が少ないにもかかわらず、気候変動の影響を大きく受ける島嶼国にとって「気候正義」の問題となっている。マグロ資源の分布変化は、島嶼国の経済に深刻な影響を与える可能性がある。
外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。
目標14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し対処する。 14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。 14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。 14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する**。 **現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉およびWTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。 14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。 14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。 14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。