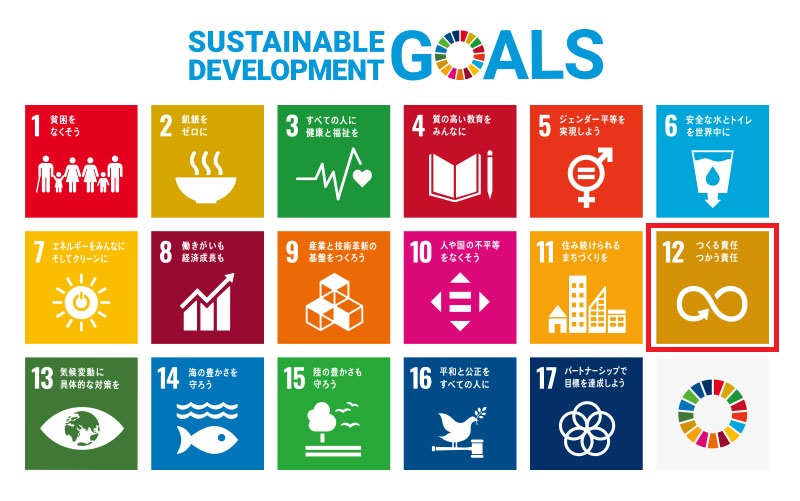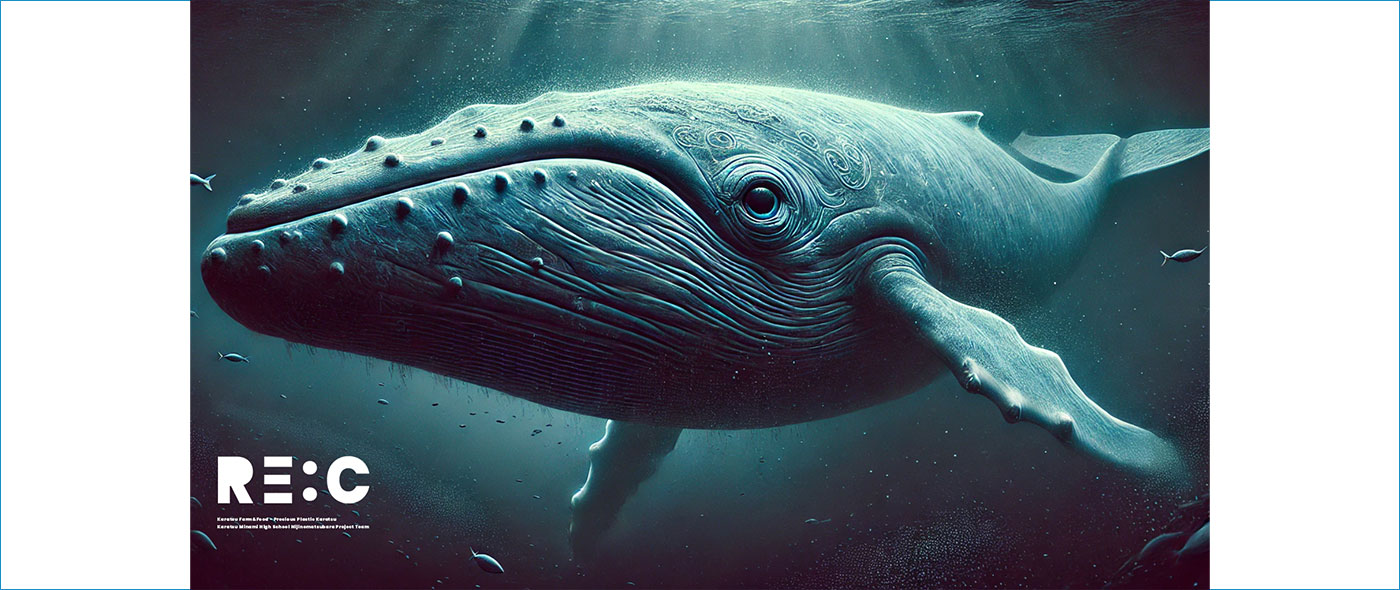ビールの麦芽粕をアップサイクルした再生紙 売上金の一部をこども食堂へ寄付
大阪シーリング印刷株式会社は、オリオンビール株式会社と共同で再生紙を開発しました。
シール・ラベル、フィルム製品、紙器パッケージ、販促ツールまでをワンストップで製造する大阪シーリング印刷株式会社(本社:大阪市天王寺区、代表取締役社長:松口 正)は、オリオンビール株式会社(本社:沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO:村野 一)と共同で再生紙を開発しました。
オリオンビールの醸造過程で発生する「麦芽粕」を紙の原材料の一部に置き換えた再生紙を、山陽製紙株式会社(本社:大阪府泉南市、代表取締役:原田 六次郎)の協力を得て開発しました。同社がその再生紙を活用して名刺を製作し、オリオンビールへ販売。その売上金の一部を子どもたちの学習支援や地域交流の場を提供している「さくら教室(旧 名護こども食堂)」へ寄付します。オリオングループは、自社の麦芽粕を使用した名刺を「サステナビリティの理念を伝えるツール」として活用します。廃棄物を有効活用した環境負荷軽減と子どもたちを支援することで地域にも貢献します。
同グループでは、環境負荷の少ない印刷方式や設備導入の推進、CO2排出量削減や環境配慮型製品の開発を強化しています。また、シール・ラベルの使用済み剥離紙の資源循環を普及促進する一般社団法人ラベル循環協会「J-ECOL」を4社で設立し、業界をあげた資源の有効活用や環境負荷低減にも取り組んでいます。今回は、麦芽粕をアップサイクルさせて有効活用する「再生紙開発プロジェクト」に賛同し、参加しました。
同グループは、さまざまな環境の変化に対応し、社会課題の解決と事業活動の両立を図ることで持続可能な社会の実現を目指す、「サステナブル経営」を行っています。事業活動を通じて経済 ・社会・環境の調和を念頭に、サステナビリティに関する4つの方針、①環境、②お客様、③社会・地域貢献、④人財活躍・育成を掲げてSDGsに取り組んでいます。本件は、③社会・地域貢献の「SDGs活動を積極的に働きがいと成長の調和を進める」取組みの一環です。
オリオングループは、沖縄をはじめとする社会全体とグループの持続的な発展に向け、5つのテーマ(「沖縄の自然との共生」「沖縄と地域社会の発展」「顧客への責任」「多様な人財の活躍」「ガバナンス」)について、15のマテリアリティ(重要課題)を掲げ、グループのサステナビリティ経営を実践しています。
本プロジェクトは、上記マテリアリティの内、「沖縄の自然との共生 ―廃棄物や残渣の有効活用」、及び「沖縄と地域の発展 ―沖縄創成と企業市民活動(地域貢献)の推進」に紐づいています。
(オリオングループのサステナビリティ https://disclosure.orionbeer.co.jp/)
オリオンビール 会社概要
社名:オリオンビール株式会社
所在地:沖縄県豊見城市字豊崎1番地411
代表者:村野 一
事業内容:酒類清涼飲料事業、観光・ホテル事業
主力製品:ビール類、RTD (Ready to drink)、フルーツワイン、清涼飲料
山陽製紙 会社概要
社名 :山陽製紙株式会社
所在地 :大阪府泉南市男里6-4-25
代表者 :原田 六次郎
事業内容:製袋用クレープ紙の製造および製袋関連資材の販売、包装用クレープ紙の製造及び鉄鋼、電線用包装関連資材の販売、自社ブランド商品(SUMIDECO、crep、PELP!)の企画、販売、電子部品用層間紙の製造及び関連資材の販売、その他オーダーメイド再生紙の製造
大阪シーリング印刷 会社概要
社名:大阪シーリング印刷株式会社
所在地:大阪府大阪市天王寺区小橋町1-8
代表者:松口 正
創業:1927年
事業内容:シール・ラベル、フィルム製品、紙器パッケージの製造・販売およびラベリングシステムの販売
URL:https://www.osp.co.jp/index.html
OSPホールディングス 会社概要
社名:株式会社OSPホールディングス
所在地:大阪府大阪市天王寺区味原本町6-8
代表者:松口 正
設立:1969年
事業内容:当該企業グループの経営企画・管理並びにそれらに付帯する業務
URL: https://www.osp-holdings.co.jp/
SDGs目標12「つくる責任つかう責任」とありますが、そもそも具体的にはどういったことなのでしょうか?
国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。
目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する
12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。 12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフ スタイルに関する情報と意識を持つようにする。 12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 12.c 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境 への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。