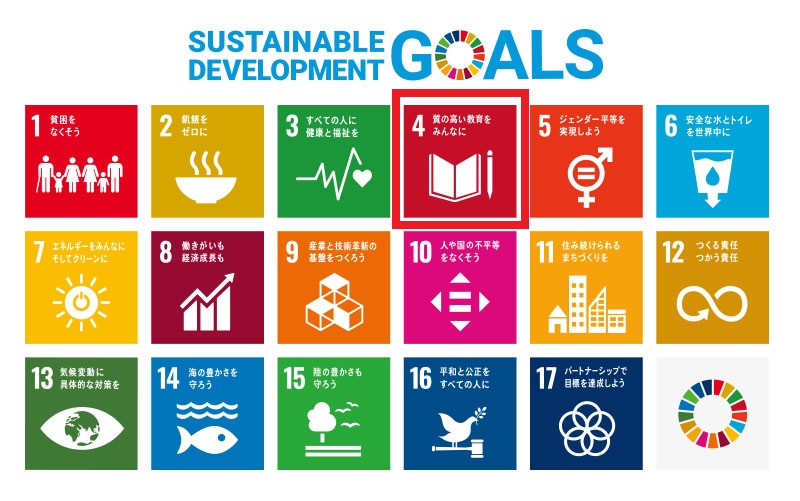川崎市立橘高等学校の生徒が脱炭素社会やプラスチック資源循環の実現を目指す事業者に対して、取組提案を実施しました!
市立橘高等学校の生徒が、事業者8社が抱えている脱炭素社会やプラスチック資源循環実現のための課題に対し、現状を調査・探究し解決策を提案しました。
川崎市立橘高等学校では、生徒がSDGsの実現に向けた視点で自分の興味や関心があるテーマについて課題設定し、探究学習を進めています。
今回、市立橘高等学校の生徒の2、3年生が、事業者8社が抱えている脱炭素社会やプラスチック資源循環実現のための課題に対し、現状を調査・探究し、更なる取組の推進につながる解決策を各事業者へ6月23日(月)に提案しました。
今後、一部の提案については、11月13日(木)に開催される第18回川崎国際環境技術展の特別企画において、生徒たちから取組結果を発表します。
実施日時
令和7年6月23日(月)14時35分から16時25分まで(6,7校時)
会場
川崎市立橘高等学校 全日制(川崎市中原区中丸子562・校長 大川 一幸・全校生徒 818名)
出席者
川崎市立橘高等学校: 2、3学年生徒 (542名)
事業者: 脱炭素アクションみぞのくち推進会議やかわさきプラスチック循環プロジェクトに参加している事業者など 8社
株式会社川崎フロンターレ:ファン・サポーター、市民に伝える環境問題への取り組みに関する課題
川崎未来エナジー株式会社:再生可能エネルギーが「当たり前」の世の中に
富士通株式会社:市民の環境行動がつくる脱炭素社会
株式会社丸井グループ:脱炭素アクション!マルイファミリー溝口の社会課題解決の取り組み
株式会社JEPLAN:みんな参加型の循環型社会!
味の素株式会社:「資源循環に向けた使用済みマヨネーズボトルの回収実証実験について」
キユーピー株式会社 :「資源循環に向けた使用済みマヨネーズボトルの回収実証実験について」
アミタホールディングス株式会社:MEGURU STATION®について
生徒の主な提案内容
●マヨネーズボトルのリサイクルの促進アイデアとして、個人からの回収ではそれほど集まらないので、たこ焼き屋さんなどと協力して、お店で使ったボトルを回収する。
●取り組み内容を、電車の広告やSNSを活用して発信する。
●市民向けにワークショップを実施し、取り組み理解を促す。
上記のような、事業者が実施している取組を知ってもらう方法やリサイクルの取組を広げる方法などについて、生徒から提案が行われました。また、以下のような学校教育への提案もありました。
●リサイクルに興味をもってもらうために、「牛乳パック」⇒「トイレットペーパー」や「ペットボトル」⇒「服」のように、「ごみや資源物」と「リサイクルした物」を組み合わせる「リサイクル神経衰弱」のゲームを学校教育に取り入れてみる。
これまでの経緯
令和7年4月
・環境局職員による学習ガイダンスを実施する。
・2、3年生混成のグループで学習の進め方を確認する。
4月21日
・事業者が抱えている脱炭素社会やプラスチック資源循環実現のための課題について生徒たちに説明する。説明を受けて、生徒たちが話し合いながら探究課題や学習計画を策定する。
4月~5月
・生徒たちが調べ学習や課外学習を通して現状を把握し、課題解決に役立つ情報を収集する。
・収集した情報を比較、分類、序列化、関連付けして考え、生徒たちが課題解決策について話し合う。
6月
・生徒たちが課題解決策の妥当性を検討し、必要であれば再度情報の収集を行う。
・情報の収集、整理・分析そして課題解決策まで、一連の学習内容についてまとめる。
6月23日
・生徒たちが課題解決策等を事業者に発表。事業者からフィードバックを受ける。
当日の写真
●高校生ならではの発想で、サステナブルを楽しく遊びながら学ぶワークショップを提案してもらえました。今後、ホームゲームで実現していきたいと思います。(株式会社川崎フロンターレ)
●授業を機に、若者らしく探求を深め、未来を切り拓くことを期待する一方、若者へ良い形でバトンを渡すのは我々大人の責任だと改めて感じました。(川崎未来エナジー株式会社)
●ごみ問題は今現在も大きな課題ですが、将来的な課題でもあると感じました。今後も、SDGsに関心をもって、自ら行動できるようにしていきたいです。今回の学習を通して、視野を広げることができました。(2年生)
●再生可能エネルギーの普及はこれからの世界には欠かせないものだと思ったので、しっかりと関心をもち、身の回りで出来ることであれば積極的に取り組みたいです。今回お話を聞いた事業者が取り組んでいることは、他の環境課題の解決にもつながると思うので生かしていきたいです。(3年生)
一部の提案について、11月13日(木)に開催される第18回川崎国際環境技術展の特別企画において、市立橘高等学校生徒たちから取組結果を発表します。
外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。
目標 4 . すべての人々への、包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する
4.1 2030 年までに、すべての女児及び男児が、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 4.2 2030 年までに、すべての女児及び男児が、質の高い乳幼児の発達支援、ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 4.3 2030 年までに、すべての女性及び男性が、手頃な価格で質の高い技術教育、職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 4.4 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事 及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 4.5 2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 4.6 2030 年までに、すべての若者及び大多数(男女ともに)の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 4.7 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 4.a 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 4.b 2020 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 4.c 2030 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員養成のための国際協力などを通じて、資格を持つ教員の数を大幅に増加させる。