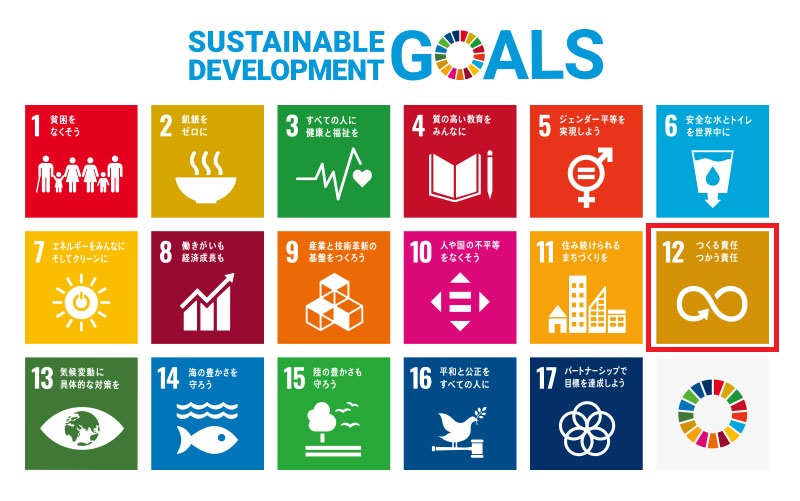持続可能な農業の未来を切り拓く「GAP Japan アワード 2025」受賞者決定
一般財団法人 日本GAP協会は、GAPの普及を推進し、持続可能な農業の未来を切り拓く、優れた取り組みを表彰する「GAP Japan アワード 2025」の受賞者を決定しました。
一般財団法人 日本GAP協会は、GAP(Good Agri cultural Practices)の普及を一層推進し、持続可能な農業の未来を切り拓く、優れた取り組みを表彰する「GAP Japan アワード 2025」の受賞者を決定しました。
本年度の受賞者は、
・JAおおいた GAP研究会(大分県)
・株式会社農流研(茨城県)
・株式会社光ファーム(茨城県)
の3団体です。
受賞者は、11月14日の「GAPとSDGs農業の日」に開催されるシンポジウム「GAP Japan 2025」で表彰されます。
年に一度、GAPの普及を一層推進し、持続可能な農業の未来を切り拓く、優れた取り組み事例を表彰するもので、「GAP Japan アワード 2025」選考委員会において、3例の優良事例を選定しました。
JAおおいた GAP研究会(大分県)
「JAの組織力で持続的成長を図り、JGAP団体認証を拡大」
受賞のポイント
2016年の「GAP普及大賞」受賞時の69農場から、2025年には161農場にまで団体を拡大。
総勢85名もの指導員体制を整え、職員の異動にも対応できる仕組みを構築するなど、JAの組織力によりJGAPを持続的に拡大している点が評価されました。
活動概要
JAおおいた GAP研究会は、2016年に品目毎の団体を統合する形でJGAP団体認証を取得。設立当初の69農場から現在は161農場20品目に拡大しました。
85名の指導員が営農指導と一体でGAPを推進し、内部監査マニュアルも改訂して事務局となるJAの人事異動にも対応可能な仕組みを整備。
さらに、日本農業新聞への寄稿や農林水産祭でのブース出展、飲食店とのコラボによるメニューフェア開催など、消費者への発信も積極的に進めています。
JAおおいた GAP研究会:https://jaoita.or.jp/agriculture/farming
株式会社農流研(茨城県)
「資材販売から生産者の育成、流通まで、JGAPを活用して地域農業を牽引」
受賞のポイント
資材販売に加え、顧客である生産者育成の観点からJGAP取得を指導し、さらには生産者を組織化して販売を行う団体を設立。
資材会社が主導してバリューチェーンをつなげ、連携してGAPの取り組みを推進している点が評価されました。
茨城・千葉・群馬・埼玉に5団体を組織し、うち2団体でJGAP団体認証を取得。個別のJGAP認証農場も加え、38農場・20品目以上を扱うGAPの広域ネットワークを形成しています。
活動概要
株式会社農流研は、農業資材販売店「農家の店しんしん」を展開するアイアグリ株式会社の事業会社です。
資材販売にとどまらず、生産者育成の観点から、JGAP認証の取得と組織化による販路確保を両立させる仕組みを構築。「いばらき農産物流通研究会」、「常総農流研」で団体認証を取得し、個別認証の農場も加えた38農場が20品目以上を出荷しています。
さらに、営農指導を行うNPO法人農業支援センターを設立し、セミナーや巡回等を通じて認証取得を支援。そのようにして実現された農流研は、資材会社が生産者へのGAP指導から販売まで、組織力で取り組むユニークなモデルとして、地域農業の持続可能性に寄与しています。
株式会社農流研:https://www.noryuken.com/
株式会社光ファーム(茨城県)
「100年続く農業経営を目指して、JGAPを活用した人材育成と組織づくり」
受賞のポイント
GAPを人材育成と組織づくりに活用し、従業員の成長と定着率を高める仕組みを構築した点に加え、地域農業者のJGAP団体認証取得も牽引。
自らの経営の安定と地域への波及効果を両立している点が評価されました。
活動概要
茨城県境町の株式会社光ファームは、米とそばを生産する農業法人です。
「持続的な営農には、働きがいのある職場づくりが不可欠」との考えから、JGAPを人材育成と組織づくりの柱とし、2019年にJGAP認証を取得しました。
JGAP指導員を核とした組織作りからの従業員教育の徹底、仕事のリストアップと見える化、人事評価への「GAPの徹底」の組み込みにより、従業員が理念に沿った行動を実践し、さらには賃金への反映によってモチベーション向上にもつながっています。
また、農業者組織の会長として地域農業者13名のJGAP団体認証をリードし、地域のGAP普及にも寄与しています。
株式会社光ファーム:http://hikarifarm.jp/
齋藤 一志(公益社団法人 日本農業法人協会 会長)
田口 光弘(農研機構 農業経営戦略部 フードチェーンユニット ユニット長)
針原 寿朗(住友商事株式会社 顧問/日本GAP協会 評議員/元農林水産省 農林水産審議官)
GAPとはGood Agricultural Practicesの頭文字を取ったものであり、農産物を生産するうえで生産者が守るべき取り組みのことを指し、「良い農業の取り組み」と訳されます。
日本GAP協会が運営するJGAP/ASIAGAPは、食品安全、環境保全、労働安全、農場管理、人権の尊重、家畜衛生やアニマルウェルフェア(動物福祉)の取り組みを基礎とした農場の認証制度であり、持続可能な農業の実現、SDGs の推進に大きく貢献するものです。
農林水産省においてもGAPの推進を重要な政策課題としているところであり、多くの食品事業者から支持されるとともに、2025年の大阪・関西万博や2027年の国際園芸博覧会における調達コードにも採用されています。
一般財団法人 日本GAP協会について
日本GAP協会は、JGAP/ASIAGAPという2つの認証制度の開発、運営および普及活動を行う一般財団法人です。
食の安全、安心、持続可能な農業の実現により、広く社会に貢献することを目的としています。
国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。
目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する
4.1 2030 年までに、すべての女児及び男児が、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 4.2 2030 年までに、すべての女児及び男児が、質の高い乳幼児の発達支援、ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 4.3 2030 年までに、すべての女性及び男性が、手頃な価格で質の高い技術教育、職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 4.4 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事 及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 4.5 2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 4.6 2030 年までに、すべての若者及び大多数(男女ともに)の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 4.7 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 4.a 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 4.b 2020 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 4.c 2030 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員養成のための国際協力などを通じて、資格を持つ教員の数を大幅に増加させる。